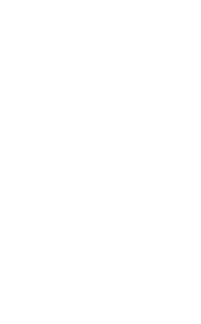- ダックスフンドではない犬種なのに、椎間板ヘルニアと診断されました。なぜでしょうか?
- 2025/08/18
-

-
 ダックスフンドではない犬種なのに、椎間板ヘルニアと診断されました。なぜでしょうか?
ダックスフンドではない犬種なのに、椎間板ヘルニアと診断されました。なぜでしょうか? ダックスフンドは椎間板ヘルニアの発症率が他犬種よりも高いので目立ちますが、全ての犬種で椎間板ヘルニアは発症する可能性があります。
ダックスフンドは椎間板ヘルニアの発症率が他犬種よりも高いので目立ちますが、全ての犬種で椎間板ヘルニアは発症する可能性があります。
椎間板ヘルニアは全ての犬種で起こる可能性があります。
ダックスフンドにしか発症しないわけではありません。
椎間板ヘルニアの生涯有病率は、犬全体で3〜4%程度の確率と言われていますが、ダックスフンド単独では20〜60%にのぼります。
生涯有病率とは、軽度・重度に関わらず、その疾患が一生涯に発症する確率のことです。
ダックスフンドの数値が飛び抜けて高いために誤解されやすいのですが、全犬種の3〜4%という数値もそれほど稀な疾患とは言えないことを示しています。
つまり、椎間板ヘルニアはダックスフンドにだけ起こる疾患ではないのです。
また、椎間板ヘルニアの発症原因が、ダックスフンドに代表される「四肢が短く胴が長い犬種」の「体型」にあると思われる方が多いのですが、それは誤解です。
椎間板ヘルニアが発症しやすいかどうかは、遺伝的素因が深く関係していると考えられています。【椎間板ヘルニアとは?】
脊椎(いわゆる背骨)は、頚椎(首の骨)7個、胸椎13個、腰椎7個、仙椎3個、尾椎(犬種や個体による差あり)の30個以上の「椎骨」から構成されています。
個々の椎骨の間のクッションの役割を担っているのが椎間板で、平らな円板状の形態です。
この椎間板が変性して本来の位置からはみ出し、脊椎内を通る神経である「脊髄」に圧迫障害や損傷を引き起こすのが椎間板ヘルニアです。
( ※ ヘルニアとは、臓器や組織が本来の位置から突出・変位することです)
椎間板は加齢とともに変性しやすくなるため、中年齢以後の全ての犬種で椎間板ヘルニアは発症する可能性があります。
ところが、若齢でも椎間板が変性しやすい遺伝的素因を持つ犬種群があり、その代表例がダックスフンドなのです。
椎間板はその中心部の「髄核」と、髄核の周囲を囲む「線維輪」から構成されています。
ダックスフンドなどは、若齢でも椎間板の髄核の変性が始まるため、椎間板ヘルニアの発症率が高いのです。
ダックスフンドに多い、椎間板の髄核が突出するタイプは「ハンセンⅠ型椎間板ヘルニア」と呼ばれ、急性に症状が進行しやすいのが特徴です。
線維輪が変性・突出するタイプは「ハンセンⅡ型椎間板ヘルニア」と呼ばれ、中高齢のイヌで発症することが多く、数週間〜数ヶ月かけて徐々に進行します。
脊髄の障害の程度によって症状は異なりますが、背部の痛みや四肢の麻痺などが起こりやすくなります。
急性の後肢麻痺はハンセンⅠ型のダックスフンドに多いと言われています。
後肢の不完全〜完全麻痺は早急に手術などの治療を実施しなければ回復しない場合が少なくありません。
椎間板ヘルニアの確定診断にはMRI (磁気共鳴画像;Magnetic Resonance Imaging)などが必要ですが、MRI診断装置を備えている動物診療施設は限られています。
このため、椎間板ヘルニアを疑う場合はできるだけ早く、MRIによる診断能力が高い動物高度診療施設などへの紹介を受けることが好ましいでしょう。
検査の結果、椎間板ヘルニアの程度に応じて手術が適用される症例と、手術の必要が無い症例があります。
手術が不要の症例でも、ケージレスト(ケージ内などで厳密な運動制限をすること)が必要な場合が多いでしょう。【椎間板ヘルニアを起こしやすいのは「軟骨異栄養性犬種」】
専門的な用語になりますが、「軟骨異栄養性犬種」と呼ばれる犬種群があります。
「軟骨異栄養性」とは、生体内の軟骨組織が変性しやすいことを意味します。
「軟骨異栄養性犬種」では、椎間板の中心部にある髄核が生後1〜2年までに変性しやすく、結果的に椎間板ヘルニアが若齢でも発症しやすいため、椎間板ヘルニアの生涯有病率が高くなるのです。
これに対し、「非軟骨異栄養性犬種」(軟骨異栄養性犬種以外の犬種)は加齢とともに椎間板が変性・突出しやすくなりますが、若齢では椎間板の変性はまだ起こりにくいため、椎間板ヘルニアは中年齢以後に発症しやすくなります。
「軟骨異栄養性犬種」はダックスフンド、ペキニーズ、フレンチ・ブルドッグ、ビーグルなどが知られていますが、それ以外にも様々な犬種が該当します。
これらは椎間板ヘルニアが若齢から発症しやすい代表的な犬種です。
現実に、筆者も上記犬種の椎間板ヘルニア症例を全て経験しています。【「軟骨異栄養性犬種」と「骨軟骨異形成犬種」】
前述の椎間板ヘルニアが起こりやすい「軟骨異栄養性犬種」とは別に、「骨軟骨異形成犬種」という犬種群があります。
両者とも似た言葉なので混同しやすいかもしれません。
「骨軟骨異形成」とは、骨や軟骨の変形が起こることで、四肢が短いのが特徴です。
骨軟骨異形成には、「線維芽細胞増殖因子(fibroblast growth factor)遺伝子」(FGF遺伝子)が関与すると考えられています。
イヌではこのFGF遺伝子が第18染色体上に存在すると、骨軟骨異形成が起こると考えられ、四肢が短い特徴が現れます。
「骨軟骨異形成犬種」はダックスフンド、ウェルシュ・コーギー、バセット・ハウンドなどが代表例です。
一方、椎間板ヘルニアが発症しやすい遺伝にも、「骨軟骨異形成犬種」と同様にFGF遺伝子が関与している可能性が指摘されています。
第12染色体上にFGF遺伝子が存在すると、椎間板ヘルニアの発症率が高いことがわかっていますが、その代表例がダックスフンドやビーグルなどです。
FGF遺伝子が第12染色体上と第18染色体上の両方に存在するダックスフンドなどは、「椎間板ヘルニアが発症しやすい性質」と「骨軟骨異形成の特徴である四肢が短い外観」の両方の遺伝を兼ね備えてしまっているということが言えるでしょう。
一方、第12染色体上だけにFGF遺伝子が存在する犬種では、椎間板ヘルニアは発症しやすいですが、骨軟骨異形成は起こらないので、四肢が短くなることはないのです。
「椎間板ヘルニアが発症しやすい『軟骨異栄養性犬種』の全てで、第12染色体上にFGF遺伝子が存在するか否か」は、まだ確定情報を得ていませんが、「軟骨異栄養性犬種」と「骨軟骨異形成犬種」との関係性を遺伝子レベルで証明できる可能性はあるかもしれません。
冒頭で記しましたとおり、ダックスフンドが椎間板ヘルニアを発症しやすいのは「『四肢が短く胴が長い体型』のため脊椎に負担がかかるのが原因」と思われている方が世間一般では多いようですが、それは誤りです。
正確には、ダックスフンドは「椎間板ヘルニアが発症しやすい遺伝」と「四肢が短くなる遺伝」の両方を受け継いでいると考えられています。
なお、ネコでもスコティッシュ・フォールドの骨軟骨異形成は遺伝性疾患の代表例として有名です。
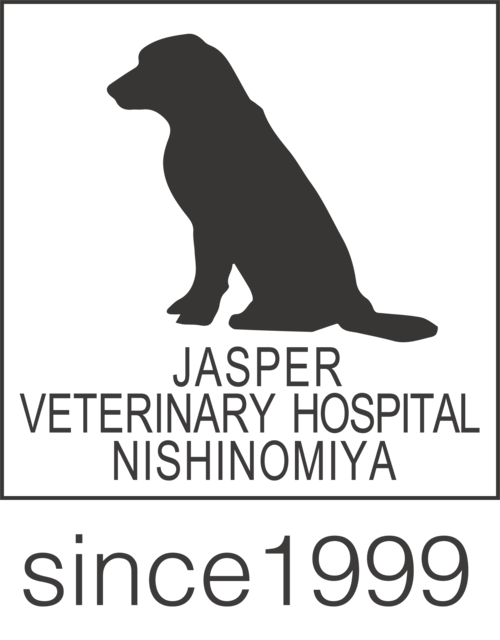
Close