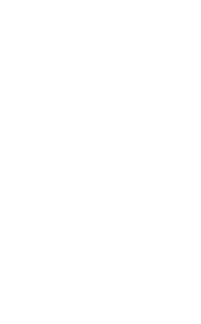- 水を飲み過ぎると下痢になりますか?
- 2025/09/26
-

-
 水を飲み過ぎると下痢になりますか?
水を飲み過ぎると下痢になりますか? 可能性は否定できませんが、現実には他の原因で下痢が起きている場合が多いと考えられます。むしろ飲水量が増えているならば、その原因が問題です。
可能性は否定できませんが、現実には他の原因で下痢が起きている場合が多いと考えられます。むしろ飲水量が増えているならば、その原因が問題です。
その動物の消化・吸収能力を超える多量の食物・水を摂取すると軟便・下痢を起こす可能性はあります。
ただし、イヌやネコなど家庭動物の多くは、基本的に飼い主さんが与えた量の水しか飲まないため、水の飲み過ぎが原因と考えられる下痢は起こりにくいのが現実です。
仮に無制限に食餌や水を与えたとしても、好きな食べ物は食べ過ぎるかもしれませんが、健康な動物であれば無味無臭の水を延々と飲み続けることはあまり見られません。
筆者が実際に飼育してきたイヌ・ネコでも、毎日必要量よりもやや多めの水を提供しますが全量を飲み干すことは無く、毎日ほぼ同じ量の水を飲み、毎日同じような量の水が残ります。「水を飲み過ぎる」ということ自体が、現実には多々起こることではないのです。
何らかの理由で一時的に水を飲み過ぎたことが原因で軟便・下痢が起きたとしても、その場合はおそらく一過性で、飲水量が普段どおりに戻れば下痢もほどなく回復すると予想されます。
【結果として起きた一過性の下痢よりも「なぜ多量の水を飲んだのか?」が問題です】
例えば「濃厚な味付けの食品」を食べてしまった後には、水を多量に飲む可能性があるかもしれませんが、その食品をやめれば飲水量も通常に戻るでしょう。
この場合は、下痢が起きたとしても飲水量の問題だけでなく「濃厚な味付けの食品」の濃厚な成分が下痢の原因である可能性も充分あり得ます。
そもそも動物がなぜ「濃厚な味付けの食品」を食べてしまったのか(拾い食い?誤って与えた?など)、その問題点を検証する必要はありますし、動物の飲水量が増加する他の原因が見つかれば、その検証や対策も必要です。【家庭内で飲水量が増える理由が見つからなければ、病気の症状かもしれません】
思い当たる理由が無いのに、動物が普段の飲水量では足りずに多量の水を求め続ける場合は病気の症状である可能性が高く、下痢症状の有無に関わらず動物病院で受診してください。
フードに含まれている水分量にもよりますが、健康に問題が無ければ1日の平均的な飲水量はイヌでは「体重1kgあたり50〜70ml」、ネコは「体重1kgあたり20〜40ml」が目安になります。
(ネコの1日の飲水量は、インターネットなどの情報によってかなり数値のバラツキが見られますが、上記の「体重1kgあたり20〜40ml」は、比較的信頼度が高いと思われる情報と、筆者が実際に飼育してきたネコたちのデータを基にした数値です。)
過剰な量の水を飲む症状を「多飲」と呼びます。
イヌでは1日の飲水量が「体重1kgあたり100ml」を継続して超えていると病的な「多飲」であると考えられ、動物病院で受診する必要があります。
「体重1kgあたり100ml」とは、平均的なイヌの飲水量の1.5倍〜2倍に相当します。
例えば体重5kgのイヌであれば1日に500mlを超える水を、毎日のように飲むのは「多飲」に該当します。
ネコの飲水量はイヌよりも少ないのが一般的で、普段食べているのがドライフードかウェットフードかによっても違いますが、1日の飲水量が「体重1kgあたり60〜70ml」を連日超えていると「多飲」の疑いがありますから、動物病院で受診してください。
具体的には体重3kgのネコなら、1日に200ml以上の水を毎日継続して飲んでいると「多飲」を疑います。
ただし、ネコに多い尿路結石対応のフードによっては、濃度が低い尿(薄い尿)を排出させるために意図的に飲水量が増えるような組成のものもあるため、一般のフードよりも飲水量・尿量が多いかもしれません。
飲水量が増える代表的な疾患としては「糖尿病」「慢性腎臓疾患(主にステージ2)」「副腎皮質ホルモン亢進症(クッシング症候群)」「甲状腺機能亢進症」などの可能性があります。
不妊手術を受けていないメスの動物では、子宮の病気でも飲水量が増える場合があります。
ただし、上記のように飲水量が増えることが知られている疾患でも、その症状は増えた飲水量に比例して尿量も増える「多飲・多尿」です。
「多飲・下痢」ではありません。【下痢は腸管の不調を疑います】
下痢は多くの場合で腸管の不調を示す症状です。
腸管が正常であれば、飲水量が多少増えても、すぐに下痢を起こすとは限りません。
吸収した水分が尿として処理・排出されますから、尿量は増えるでしょう。【下痢の原因】
下痢の原因は「細菌感染性」「ウイルス感染症」「寄生虫」「アレルギー」「慢性腸症」「腫瘍」など様々な可能性があり、「食べ物の変更」や「ストレス」がきっかけで軟便・下痢が起こることもあります。
1症例に複数の原因が関係している場合もあり得ます。
下痢という症状だけでひとつの原因に絞り込むことは簡単ではありません。
例えば動物が旅行先で下痢を起こしたとして、「旅行の疲れやストレス」「旅行先で慣れない食物を食べた」などが原因として疑われるのは容易に想像できますが、「胃腸障害を起こす細菌・ウイルス感染」が起きている可能性もあります。
私たちヒトや動物は無菌室で生活しているわけではありませんから、常に細菌やウイルスの感染が起こる可能性があります。
特に動物は様々な物のにおいを嗅ぎ、舌で舐めることもしばしばありますから、旅行先で胃腸障害を起こす細菌などが口から侵入・感染しても不思議ではありません。
もしも旅行中に水を多めに飲んだ後に下痢が起きたという事実があっても、飲水量以外の原因が否定できるわけではないのです。
水の飲み過ぎというやや特殊な条件よりは、感染性の下痢などの方が発生確率が高いと考えるのが自然でしょう。
あるいは別の例として、ジュースやスープ・だし汁など味付けをした液体であれば、その味を求めて過剰に飲んでしまう可能性はあるかもしれませんが、この場合は下痢が起きたとしても原因が過剰な飲水量とは限らず、普段飲まないジュースやスープなどの成分が胃腸を刺激して下痢が起こる可能性も考慮するべきでしょう。
同様に水分が豊富なフルーツなどを食べた後に下痢が起きた場合も、含まれている水分量の問題以外に、食材の成分などを下痢の原因として疑う必要があります。
また、原因が何かに関わらず、ある程度下痢が続くと喪失水分が多くなり、結果的に普段よりも飲水量が増えるケースはあるため、これを錯覚して水を多く飲むと下痢しやすいような誤解が生まれるのかもしれません。【あえて飲水に関連しての問題を疑うなら…】
海水を飲むと軟便・下痢が起こるケースがあります。
海水の塩分濃度は約3.5%で、ヒトやイヌ・ネコなどの生体の体液バランスよりもかなり濃厚なため、腸管内の浸透圧に影響が出ることが考えられます。
よほど多量の海水を飲んだのでなければ軟便・下痢は一過性で、ほどなく回復すると思われますが体調の観察はしておくべきです。
また、ヒトでは俗称で「水あたり」と呼ばれる嘔吐や軟便・下痢などの胃腸障害がありますが、これは普段飲まない「硬水」(ミネラル濃度が高い水)を旅行先などで飲んだことにより胃腸が刺激された場合や、細菌やウイルスなどに汚染された水を飲んで発症した「感染性胃腸炎」を意味する場合が一般的です。
水の飲み過ぎを「水あたり」と呼ぶことはあまりないようですが、これはあくまで俗称であるため、感染性胃腸炎も水の飲み過ぎも区別せず「水あたり」という言葉遣いをされる方は世間にいらっしゃるかもしれません。
医学用語で「水中毒(water intoxication)」と呼ばれるのは、かなり過剰な量の水分(平均的な飲水量の数倍程度?)を摂取した結果、体内のナトリウムなどの濃度が異常に低くなったために起こる障害で、脳浮腫や意識障害など生命の危険があります。
現実には一般的な家庭動物の生活で水中毒が起こる可能性は低く、多少飲水量が増加した程度では水中毒を心配する必要は無いと考えて良いでしょう。
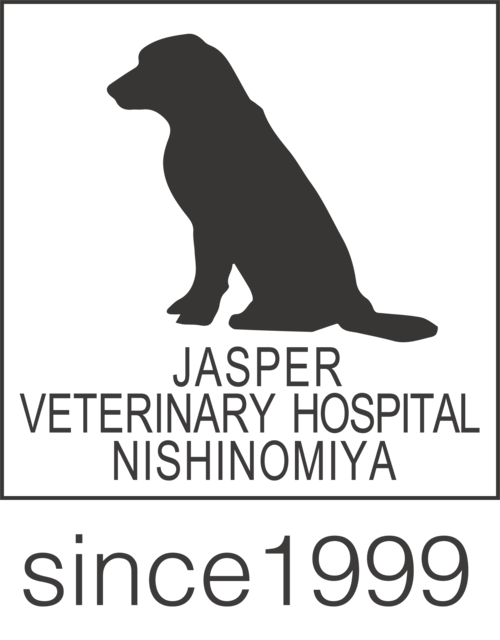
Close