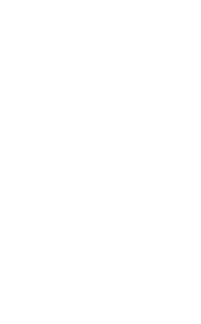- ウサギの寿命を調べると情報によってかなり違いがあります。なぜですか?
- 2025/11/19
-

-
 ○ウサギの寿命を調べると情報によってかなり違いがあります。なぜですか?
○ウサギの寿命を調べると情報によってかなり違いがあります。なぜですか? ウサギの飼育環境は近年変化しており、寿命の情報に影響が出てきている可能性があります。
ウサギの飼育環境は近年変化しており、寿命の情報に影響が出てきている可能性があります。【ウサギの飼育の歴史はイヌ・ネコと異なります】
現在の家庭で暮らすウサギは「イエウサギ」と呼ばれ、野生種である「アナウサギ」を家畜化したのが始まりだと言われています。
イヌやネコと違い、ウサギを家畜化した当初の目的は「食用」でした。
人類がイヌを最初に飼い始めたのは猟犬や番犬などとして、ネコはネズミから穀物を守るためなど「使役(仕事をさせる)」を目的に家畜化されたと考えられ、イヌの飼育の歴史は1万年以上前から、ネコは少なくとも数千年前から飼育されているようです。
その途中からは、使役だけでなくいわゆる家庭動物(愛玩動物)としても飼育されるようになったと考えられ、イヌ・ネコは家庭動物としての歴史も長いのです。
そして、イヌやネコが長期間元気で生活できるように、健康的な飼い方の工夫が長い年月をかけて重ねられてきました。
その結果、イヌやネコの飼育・健康管理法は完成度が高くなってきたと考えられ、寿命は現在も少しずつ伸びる傾向はあるようですが、ウサギの寿命についての情報に比べると変化が少なく安定しているのです。
■参考■
現在日本で飼育されることが多い小型犬種・中型犬種や猫種では、大半が10〜12歳頃には何らかの老化現象が見られるようになり、平均的には15〜16年は生きることが多く、中には20年前後生きる例もある、という状況が続いています。
筆者の経験上、イヌやネコの平均的な寿命は2000年代以後、上記とほぼ同様の傾向であると思われます。
(イヌに比べるとネコの方が長く生きる傾向があります。また、大型犬種は小型・中型犬種よりも寿命が短いと言われますが、それでもラブラドール・レトリーバーなどは15〜16年生きる例が珍しくありません。)
【ウサギの飼育の歴史的な背景】
一方、ウサギは当初食用が目的で飼育されていたので、長生きさせる必要はありませんでした。
ウサギが若いうちに肉を得ればよかったわけですから、肉質が良くなることだけを目的にして飼育されてきたと推測されます。
おそらく、ウサギの寿命が尽きるまで飼育を続けるということは現在よりも少なく、長生きさせるための工夫はそれほど追求されていなかったでしょう。
ウサギが家庭動物としての地位を獲得したのはイヌやネコに比べて最近で歴史が浅いことから、ウサギの健康長寿を目指す飼育法は今も発展途上であると考えていいのかもしれません。
ウサギの寿命についての情報にバラつきが見られるのは、飼育環境がまだ安定していないことを示している可能性があります。
1990年代のウサギの資料では、平均寿命が6〜8年と記されているものがありました。
臨床現場でみる限り、現在は10年以上生きるウサギが一般的だと思われます。
平均寿命6年と10年以上では2倍近く違うことからも、近年の食餌や飼育法など、ウサギの生活環境は改善しつつあると考えられます。
時が経てば、現在のウサギの飼育法は時代遅れで、もっと良い方法が普及している可能性もあります。
その場合には、今よりもウサギの寿命はさらに長くなっているかもしれません。
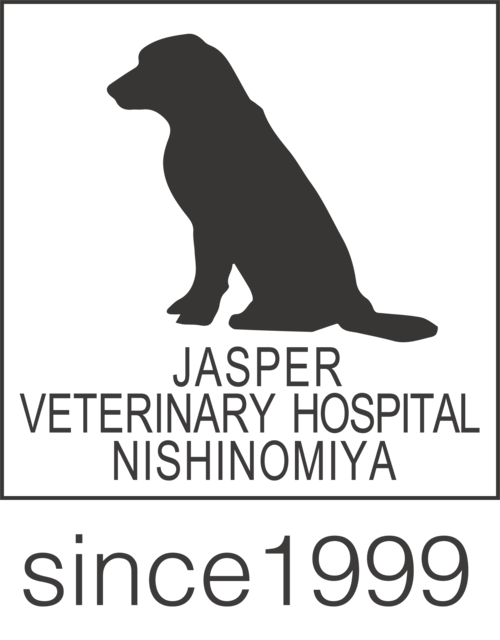
Close