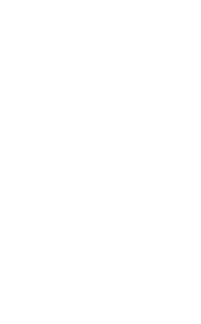- ○ステロイドについて
- 2026/01/14
-

-
世間一般では、ステロイドと言えば「ステロイドホルモン」を治療に応用する「ステロイド剤」を指すことが多いでしょう。
一方、医学・獣医学で言うステロイドであれば、私たちヒトや動物が体内に持っているステロイドホルモン全般を意味することもあります。【ステロイドホルモンとは?】
私たちの体内で働くステロイドホルモンには、女性ホルモン・男性ホルモンなどの「性ホルモン」と、副腎皮質から分泌される「副腎皮質ホルモン」があります。
さらに、副腎皮質ホルモンには「糖質コルチコイド」と「鉱質コルチコイド」の2種類があります。
これらのホルモンの分子構造において「ステロイド骨格」と呼ばれる部分が共通しているため、性ホルモンと副腎皮質ホルモンはステロイドホルモンと呼ばれます。
当然、これらのホルモンは生体や繁殖に必要であるため、私たちヒトや動物も生来持っているのです。
なお、日常でもお馴染みの「コレステロール」の分子構造にも、ステロイド骨格が含まれていますが、コレステロールがステロイド剤と同じ働きをするわけではありません。【一般的に「ステロイド剤」と呼ばれることが多いのは、副腎皮質ホルモンの「糖質コルチコイド」です】
生体に必要なホルモンの本来の働きを「生理作用」と呼びます。
同じホルモンでも、治療に応用して投与すると本来の生理作用とは異なる働きが見られることがあり、これを「薬理作用」と呼びます。
この薬理作用を期待してホルモンを治療に応用する場合があります。
ステロイドホルモンの中で、一般的にステロイド剤という名称で治療に応用されることが多いのが副腎皮質ホルモン(糖質コルチコイド)です。
参考までに、俗に言う「筋肉増強ステロイド」は、男性ホルモンの類似成分を利用するもので、上記のステロイド剤(副腎皮質ホルモン)とは異なります。【副腎皮質ホルモンの働き】
生体が持っている副腎皮質ホルモンは、「ストレスなどの負担から身体を守る」「糖の利用」「正常な血圧の維持」など、極めて重要な役割があり、このホルモンが無くては生きていけません。
ストレスがかかると、身体は自分自身を守るために副腎皮質ホルモンを働かせます。
このため、副腎皮質ホルモンは俗称で「ストレスホルモン」と呼ばれることもあります。
例えば副腎皮質ホルモンが不足すると、ストレスに耐えられず虚脱やショック状態になる可能性があるのです。
実際に体内の副腎皮質ホルモン量が病的に少なくなる「副腎皮質機能低下症(アジソン病)」では、「虚脱」「ショック症状」「不整脈」「徐脈(心拍が遅くなること)」などが見られ、放置すると死亡する恐れがあります。
このように重要な働きがある副腎皮質ホルモンですが、多過ぎても問題が起こります。
副腎皮質ホルモンが多過ぎる「副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)」が発症すると、「多飲・多尿」「腹部膨満」「活動性低下」「皮膚や被毛の状態が悪化」などの症状が見られ、細菌などの感染が起こりやすくなります。
血液検査では「肝臓関係の数値の異常」「血糖値の異常」など、様々な異常が確認されることもあります。
ホルモンが過剰な量のまま治療せずに放置すると、この場合も死に至る可能性があります。
つまり、ステロイドホルモン(副腎皮質ホルモン)は少な過ぎても多過ぎても問題が起こり、「ちょうど良いバランス」が必要なのです。【副腎皮質ホルモンをステロイド剤として治療に応用する例】
◉消炎剤
副腎皮質ホルモンを治療に応用する例としてよく知られているのは「消炎効果」を期待する場合でしょう。
炎症を鎮める副腎皮質ホルモンの薬理作用は有効性が高く、短期間の使用に限れば消炎剤として利用可能な症例も多いと考えられます。
特に外用薬で使用される「アンテドラッグ」に類するステロイド剤(副腎皮質ホルモン)は副作用が起こり難く、安全性が高いのが特徴です。
アンテドラッグとは、外用薬として皮膚に塗布するとその部位では効果を発揮しますが、皮膚からほとんど吸収しない、もしくは速やかに不活化されるために体内には薬理作用の影響が出ないように設計された薬剤のことです。◉アレルギー治療
アレルギーとは、「本来、生体に無害であるはずの物質に対して、有害なもののように反応してしまう過剰な免疫反応」です。
アレルギーの原因物質(アレルゲン)が判明し、そのアレルゲンを患者さんの生活から排除できればアレルギー症状は軽減し、発症を防ぐことができるはずですが、現実には花粉などのように除去が困難なアレルゲンもあります。
このような場合は、過剰な免疫反応を治療によって抑制すると、アレルギー症状は軽減します。
副腎皮質ホルモンは、アレルギーの過剰な免疫反応を抑制するのに利用されることが多く、アレルギー症状の程度によって投与量の調節も可能です。
ただし、副腎皮質ホルモンを投与してもアレルギー体質が解消するわけでは無く、アレルギー症状を抑制する治療です。
一過性のアレルギー症状であれば、副腎皮質ホルモンは有効な手段であると言えるでしょう。
一方、現実のアレルギー症例では「アレルギーが発症するかどうか」「発症した場合に症状が軽度か重度か」「症状が短期間か長期間か」は個々の体質やアレルゲンの条件によって左右されます。
慢性的にアレルギー症状が見られる症例では、症状を抑制するための治療も長期になる傾向があります。
副腎皮質ホルモンは過剰な量を長期間継続投与すると副作用・副反応が起こりやすく、症例によっては使用を控えざるを得ない場合があります。
このような症例では治療薬剤として副腎皮質ホルモンではなく、「非ステロイド」の消炎剤などを選択することになります。
当院も含めて皮膚科診療施設では、アレルギー症例についてステロイド剤以外の選択肢があります。
「分子標的薬」「免疫抑制剤」「漢方薬」「抗ヒスタミン剤」などがアレルギー症例に使用される薬剤の例になります。◉自己免疫性疾患治療
自己免疫性疾患とは、「自分自身の組織や細胞に対して、免疫が攻撃してしまう疾患」のことです。
私たちヒトや動物の身体には「自分自身」と「自分でないもの」(「自己」と「非自己」と呼びます)を見分ける仕組みがあります。
外界から侵入した細菌やウイルスなどを非自己として認識し、それを排除して身体を守るのが免疫の本来の役割です。
ところが自己免疫性疾患では、非自己を排除する免疫のシステムが、自己に対して働いてしまう、つまり自分自身の組織や細胞を攻撃してしまうことで様々な症状が起こるのです。
自己免疫性疾患の治療については「免疫の過剰な働きを抑制する」という方向性において上記のアレルギー治療と似ていますが、決定的な違いがあります。
アレルギーは食物や花粉など外界からの異物(非自己)に対しての免疫の過剰な反応なので、これらの原因物質(アレルゲン)を排除できれば症状が発生しない、もしくは軽減する可能性が期待できます。
一方、自己免疫性疾患では過剰な免疫の標的が自分自身の組織(自己)ですから、標的(自己)が除去されることはないので、アレルギー症例での「原因物質を除去する対策」のような方法はありません。
自己免疫性疾患が、生涯にわたっての継続治療を必要とする可能性があるのはこのためです。
動物の自己免疫性疾患では「免疫介在性溶血性貧血(Immune-mediated Hemolytic Anemia : IMHA)」や「全身性エリテマトーデス(Systemic Lupus Erythematosus:SLE)」などがありますが、いずれも完治は難しく、症状を「コントロールする」治療が現実的な対策になります。
自己免疫性疾患の原因については諸説ありますが、現時点では未解明です。
自己免疫性疾患の治療に副腎皮質ホルモン(ステロイド剤)を応用する場合では、免疫抑制作用が期待できる投与量が必要になるため、比較的高用量の副腎皮質ホルモンを投与することになり、副作用・副反応が問題になります。
このため、症例によっては副腎皮質ホルモン単独ではなく、免疫抑制剤などと併用し、それぞれの薬剤量を減らす工夫も試されます。◉抗がん剤治療
いわゆる抗がん剤治療では、副腎皮質ホルモン(ステロイド剤)を併用するケースがしばしばあります。
副腎皮質ホルモンは、抗がん剤ではありませんが、抗がん剤治療の際に以下のような働きが期待されるため併用されることがあります。・抗がん剤などに起因するアレルギー反応の抑制
・食欲増進作用
・嘔気(吐き気)抑制
・過剰なサイトカイン(※)の抑制
・腫瘍周囲の正常な組織の炎症や浮腫を軽減
・リンパ系腫瘍の抑制 など(※)サイトカイン:
主に免疫細胞から分泌される様々な低分子タンパク質のこと。
細胞同士の情報伝達など、それぞれが特異的な生理活性を持つ。
炎症などに関与するサイトカインが過剰な場合、そのサイトカインを抑制すると炎症が軽減することが期待される。【ステロイド剤の問題:副作用】
副腎皮質ホルモンをステロイド剤として投与する場合、使用する薬剤の種類や量、期間によって副作用・副反応が見られることがあります。
特に内服・注射など全身性の投薬を実施している症例では、前述の副腎皮質ホルモンが多過ぎる「副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)」と同様の症状が見られることがあり、程度の差はありますがこれがステロイド剤の副作用と考えて良いでしょう。
一般的に気づかれやすい症状は、初期では「多飲・多尿」「細菌・真菌などの感染が起こりやすい」など、継続投薬がある程度の期間に及ぶと「皮膚や被毛の状態が悪化」などが見られることがあります。
血液検査では「肝臓関係の数値の異常」「血糖値の異常」などが確認されることもあります。
治療にステロイド剤を使用している場合はこのような変化をモニターし、副作用の程度によって対応すると思われますが、疾患によっては副作用は承知の上で継続投薬せざるを得ない場合もあります。
前述の「免疫介在性溶血性貧血」や「全身性エリテマトーデス」「悪性腫瘍」などは治療しなければ死亡する可能性も考えられるため、やむを得ず投薬を継続するケースがあるかもしれません。【よくあるステロイドの誤解】
①ステロイド剤って毒なの?
ステロイド剤はしばしば副作用・副反応が指摘されますが、中にはまるで毒物のような誤解をされている方が散見されます。
前述のとおり、ステロイド(女性ホルモン、男性ホルモン、副腎皮質ホルモン)は私たちヒトや動物に必要なホルモンで、毒ではありません。
これを治療に応用するのがステロイド剤(副腎皮質ホルモン)です。
ステロイド剤を多く使うと副腎皮質ホルモンの過剰症と同じような現象・症状が現れることがあり、これがいわゆるステロイド剤の副作用です。
一般的な治療では、必要が無ければステロイド剤を無意味に使用することはありません。
一方、どうしてもステロイド剤を使わざるを得ない疾患もあるのが現実なので、その場合は副作用が出にくいような使い方を心掛ける必要があります。
さらに、副作用が出るであろう量のステロイド剤が治療に必要な疾患もあります。
前述のように腫瘍や自己免疫性疾患などによる生命の危機を避けるためには、副作用が起こると予想される量のステロイド剤を使用しなければならない場合もあり得ます。
この場合は、治療の目的や期待される効果とともに、副作用のデメリットを患者さん(飼い主さん)と相談した上で、治療方針を決定することになるでしょう。②ステロイドってストレスの原因なの?
ステロイドホルモンである副腎皮質ホルモンが、身体をストレスなどの負担から守る役割を担っているのは前述のとおりです。
この情報を元に、副腎皮質ホルモンを俗称で「ストレスホルモン」などと呼ぶ場合がありますが、この俗称を誤解して、副腎皮質ホルモンがストレスの原因であるかのように勘違いされている場合があります。
実際には「ストレスの負担から身体を守ってくれるホルモン」であるにも関わらず、最も重要な「負担から身体を守ってくれる」の部分が省略されているためにこのような誤解が生じるのだと考えられます。
また、ステロイドの副作用の悪いイメージと、ストレスの悪いイメージを重ねてしまい、「ステロイド→『悪』→ストレス」という連想による思い込みがあるのかもしれません。
副腎皮質ホルモンはストレスから私たちを守る役割を担っている必要なホルモンであって、ストレスの原因ではありません。

Close