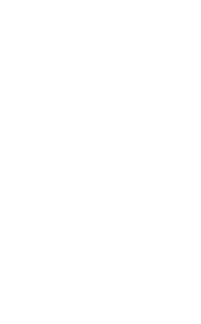- 細菌とウイルスの違いは何ですか?
- 2025/10/31
-

-
 細菌とウイルスの違いは何ですか?
細菌とウイルスの違いは何ですか? 細菌は細胞構造を持つ生物ですが、ウイルスは生物ではないと考えるのが現在の定説です。細菌もウイルスも病原体として、人間や動物の病気の原因になる可能性があります。
細菌は細胞構造を持つ生物ですが、ウイルスは生物ではないと考えるのが現在の定説です。細菌もウイルスも病原体として、人間や動物の病気の原因になる可能性があります。
病気を起こす可能性がある細菌やウイルス、寄生虫などは「病原体」と呼ばれます。
病原体が感染することによって起こる病気を「感染症」と呼びます。
人間や動物の感染症の多くは細菌やウイルスが原因ですが、細菌とウイルスは全く異なるものです。【細菌は単細胞の生物です】
細菌は細胞構造を持つ「原核生物」で、外部の栄養からエネルギーを得て細胞分裂を行い、増殖します。
原核生物とは、核を持たない単細胞生物で、最も単純な細胞構造の生物という位置づけです。
細菌の種類によって大きさは違いますが、およそ1〜10μm(マイクロメートル)( = 1 μmは1000分の1ミリメートル)程度で、肉眼では確認できない大きさです。
光学顕微鏡(通常の光源とレンズを利用する一般的な顕微鏡)の倍率400倍程度で細菌の存在はわかると思われますが、細菌の構造を観察するには1,000倍程度の倍率が必要になります。
病原性がある細菌が感染すると、人間や動物の身体で増殖することで病気が発生したり、その代謝産物に毒性がある場合でも病気や健康被害が生じます。
例えば「黄色ブドウ球菌」は普段から人間や動物の身近に存在する菌(常在菌)ですが、この菌は皮膚炎や傷の化膿を起こすとともに、エンテロトキシンという「菌体外毒素」(毒性がある代謝産物)を作り出すため、この毒素によって食中毒も発生します。
手指に傷がある人は、調理や食品を扱う作業を避けるべきであると言われるのはそのためです。
一方、人間にとって有益な代謝産物を作る細菌もあり、発酵食品などに応用される場合があります。
また、腸内細菌の中にも生体に有利な働きをする種類があり、これが俗に言う「腸の善玉菌」です。【細菌感染治療に使用されるのが「抗菌剤・抗生物質」です】
細菌を殺滅したり増殖を阻害する抗菌活性がある薬剤を「抗菌剤」と呼びます。
抗菌剤の中でも生物由来の成分は特に「抗生物質」と呼ばれることがあります。
例えばペニシリンは青カビ由来の抗生物質です。
広義の「抗菌剤」は抗生物質を含む抗菌活性がある薬剤全体を指しますが、抗生物質以外は「合成抗菌剤」もしくは単に「(狭義の)抗菌剤」と呼びます。
細菌の種類によって抗菌剤の効果は異なるため、ただひとつの抗菌剤で全ての種類の細菌の対策ができるわけではありません。
さらに近年の大きな課題として、抗菌剤が効かない「耐性菌」の問題があります。
元々は効果があるはずだった細菌と抗菌剤の組み合わせでも、細菌が薬剤耐性を得てしまうとその抗菌剤が効かなくなり、治療効果が得られない例が現実に起こりつつあります。
近い将来、耐性菌感染による死者数が、悪性腫瘍(いわゆるガン)による死者数を上回ると予測する情報もあります。
このため、耐性菌を増やさないことを目的として、不必要な抗菌剤の使用は減らすように世界的な努力が続けられています。
なお、抗菌剤・抗生物質は細菌に対する薬剤で、ウイルスに対しては全く効果がありません。【ウイルスは自己増殖できず、生物の定義に当てはまらないという考え方が現在の定説です】
ウイルスは細菌よりもさらに小さく10〜100nm(ナノメートル)( = 1 nm は1000分の1マイクロメートル)程度の大きさで、もちろん肉眼では見えません。
ウイルスは細菌と異なり、光学顕微鏡では見えません。
ウイルスの画像を得るには、電子顕微鏡によって5万倍程度の拡大倍率が必要になります。
ウイルスには生物のような細胞構造は無く、DNAやRNAなどの遺伝子をタンパク質が覆っているような構造しかありません。
ウイルスは自身で増殖することはできず、外部から栄養を取り込むこともしません。
かつて1980年代頃の専門書の記載では「ウイルスは最小の生物である」とされていましたが、現在は生物とみなさないのが有力な考え方です。
ウイルスはDNAやRNAなどの遺伝子を持つので生物と無関係とは言えない一方で、自己増殖できず生物であると定義するには不完全であり、「細胞内寄生体」などと呼ばれることがあります。
ありきたりな表現をすれば、生物と非生物の中間的な存在ということでしょうか。
ウイルスは生物の細胞に感染することで、その細胞の機能を利用して同じウイルスを複製(増殖)させます。
ウイルス感染を受けた細胞は結果的に傷ついたり破壊されることが多く、これがウイルスによる病気の発生機序になります。
余談になりますが、生物の進化にはウイルス感染によって外部からもたらされた新規遺伝情報が影響していると言われており、人間の遺伝情報であるゲノムの数%程度はウイルス由来であると考えられています。
見方を変えれば、ウイルス感染が生物の進化に影響を与え続けてきたということは、生体に侵入したウイルスの種類によっては、生体側の免疫力などで排除するのが容易ではないことを示しているのかもしれません。【ウイルス感染治療には「抗ウイルス剤」が使われます。「抗菌剤」は効きません。】
ウイルス感染の治療薬のひとつが「抗ウイルス剤」です。
抗ウイルス剤は、ウイルスが細胞に侵入・複製(増殖)・拡散するのを阻害することが期待されますが、既存の抗ウイルス剤の効果が見られるウイルス感染症は限られており、副作用が指摘されている薬剤もあります。
生体の細胞内に侵入した後のウイルスを薬剤で攻撃するためには、その薬剤も細胞内に作用する必要があるため結果的に細胞も傷つける可能性があり、これが薬剤の副反応・副作用につながる恐れもあります。
抗菌剤・抗生物質は細菌に対して効果を発揮する薬剤で、ウイルスには無効です。
消毒剤の効果はウイルスの種類によって異なり、一般的な消毒剤では不活化できない種類のウイルスもあります。
動物病院で最も強力な消毒剤を必要とする対象はイヌ・ネコの「パルボウイルス」です。
パルボウイルスはアルコール系やヨード系の消毒剤では不活化できず、比較的高濃度の次亜塩素酸ナトリウムが必要になります。
なお、冒頭のとおりウイルスは生物ではないという見解が現代の主流なので、「ウイルスを殺滅する」「殺ウイルス効果」などの「殺」という表現は適さないため、ウイルスの感染力や病原性を失活させることは「不活化」と呼びます。
ただし、例えば効ウイルス剤の効果を説明する場合に、患者さんが理解しやすいように敢えて「ウイルスを『殺す』薬です」と表現する事例はあり得るでしょう。
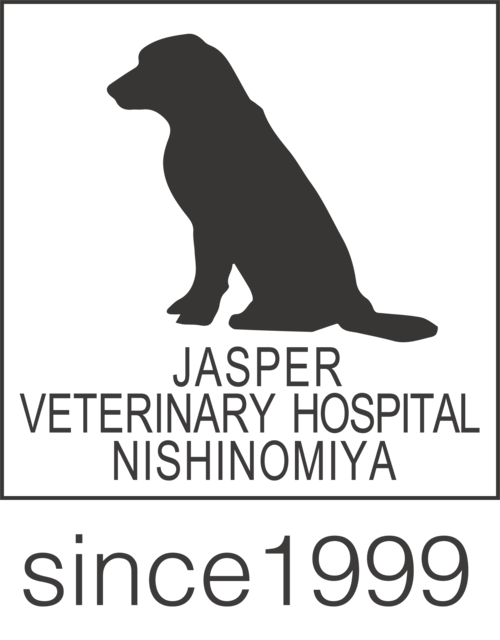
Close