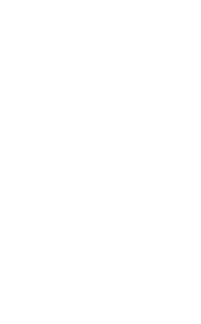- 「1日1回の飲み薬」と「1日2回の飲み薬」の違いは何ですか?
- 2025/07/23
-

-
 「1日1回の飲み薬」と「1日2回の飲み薬」の違いは何ですか?
「1日1回の飲み薬」と「1日2回の飲み薬」の違いは何ですか? 薬剤の種類によって効き方の特徴が異なるので、目標どおりの治療効果を実現するために必要な投薬量と投薬回数がそれぞれ決められています。投薬回数を守ることは大切です。
薬剤の種類によって効き方の特徴が異なるので、目標どおりの治療効果を実現するために必要な投薬量と投薬回数がそれぞれ決められています。投薬回数を守ることは大切です。
薬剤の種類や患者さんの条件によって、投薬回数は異なることがあります。
投薬回数の根拠には、薬剤の「血中濃度」と「代謝」が関係します。【血中濃度】
血中濃度とは、文字どおり血液の中に含まれた薬剤成分の濃度のことです。
投与された薬剤は血中に取り込まれ、一般的には投薬後数時間以内(時間は薬剤の種類や投与方法によって異なります)に最も濃い状態になり、その後時間の経過とともに代謝されて濃度は薄くなり、最終的に消失します。
血中濃度は投与後の時間経過によって変化します。
薬剤の効果が現れる濃度を「有効血中濃度」と呼びます。
多少の薬剤が血中にあっても、それが有効血中濃度以下なら効果は期待できません。
この効果が無い低濃度の薬剤の血中濃度を「無効域」と呼びます。
投薬直後で有効血中濃度に達する前と、薬剤が代謝されて有効血中濃度以下に低下した後は、どちらも無効域ということになります。【代謝】
ヒトも動物も食べたものがそのまま身体の構成成分やエネルギーになるわけではなく、身体の中での化学反応によって利用可能な物質に作り変えています。
食物と水、酸素を利用して、生体に必要な物質やエネルギーに変化させる化学反応を「代謝」と呼びます。
薬物などが生体内に入って役目を終えた後に、排泄しやすいような物質に分解されたり、作り変えられたりすることも代謝(薬物代謝)といいます。
薬物が体内で代謝されるスピードは、薬剤の種類や生体(患者さん)側の条件によって異なります。
【薬剤の投与回数の根拠】①代謝速度
前述のように、薬物が体内で代謝されるスピードは、薬剤の種類や生体(患者さん)側の条件によって異なります。
代謝速度が早くて、有効血中濃度が短時間しか続かない薬剤なら、効果を継続維持するために1日に何回も投与しなければならないかもしれません。
代謝速度が遅い薬剤は投薬回数が少なくて済む可能性があります。② 「時間依存性薬剤」と「濃度依存性薬剤」
抗菌剤などでは、「時間依存性薬剤」と「濃度依存性薬剤」があります。
[時間依存性薬剤]
抗菌剤であれば、菌の増殖を抑える効果が得られる最小限の血中濃度が基準のひとつになります。
これを「最小発育阻止濃度(Minimal Inhibitory Concentration ; MIC)」といいます。
投薬した薬剤の最小発育阻止濃度が、体内(血中)で維持される時間が長い方が効果が大きくなる性質の薬剤を「時間依存性薬剤」と呼びます。
このタイプの薬剤は1回の投薬量を増やしても効果の限界があり、良好な効果を得るためには、最小発育阻止濃度に達する投薬量を1日に複数回投薬する必要があります。
投与回数を減らしたり、投与を忘れたりすると、この時間依存性薬剤は予定どおりの効果が見られなくなる恐れがあります。
なお、時間依存性薬剤は前述のとおり1回の投薬量を増やしても効果の限界(上限)はありますが、これは副作用も上限があるという意味ではないので、安易な過剰投与は避けなければなりません。[濃度依存性薬剤]
薬剤の血中濃度が最も濃い時の数値を「最大血中濃度(Maximum plasma Concentration ; Cmax)」といいます。最大血中濃度が高い方が大きな効果が得られる性質の薬剤を「濃度依存性薬剤」と呼びます。
このタイプの薬剤は、1日合計の薬剤量が同じなら、2回に分けて投与するよりも1回にまとめて投与する方が効果が高いのです。
このため、安全な範囲の1日の最大量を1回投薬するのが効果的です。
濃度依存性薬剤は、指定された1回量を2回・3回に分割投与すると効果が低減してしまう可能性が高くなります。③動物種の違い
前述の薬物代謝との関連もありますが、同じ薬剤でもイヌとネコで投薬回数が異なる場合があります。
これは動物種による薬剤代謝速度の差が理由になっていることが多いでしょう。
また、副作用が起こりやすいか起こりにくいかも動物種の差があるため、これも投薬回数に影響するかもしれません。
極端な例では、ヒトやイヌ・ネコでは安全性が高い薬剤でも、ウサギには副作用・副反応が起こりやすくて投与回数を減らすどころか使用できない場合もあります。④その他
1回の投薬で十分な役割が果たせる薬剤であれば、当然投与回数は少ないはずです。
代表的なのは腸管などの寄生虫の駆除剤(駆虫剤)です。
もしも少ない回数の投薬で寄生虫がすべて駆除可能で、その後の再寄生の恐れが無ければ、継続投薬は必要無いということになります。
ただし、寄生虫の種類によってはある程度の期間の連続投薬が必要な場合があります。
また、定期的に繰り返し感染する可能性がある寄生虫なら、定期的な投薬が必要です。
定期的な投薬が必要な寄生虫対策の代表例がフィラリア予防です。【投薬量や投薬回数は医学的・獣医学的根拠に基づいて決められており、指定された量・回数を守ることは大切です。】
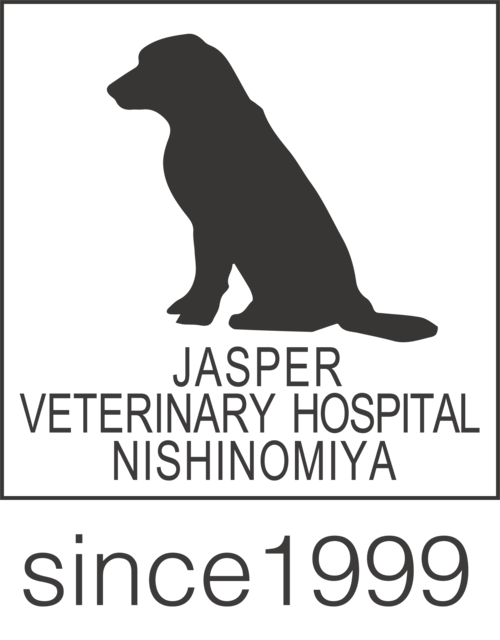
Close