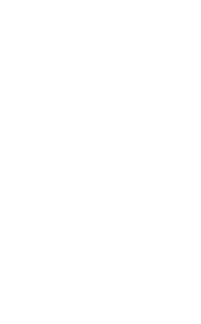- ウサギは寂しいと死ぬ?
- 2025/08/05
-

-
 ウサギは寂しいと死ぬ?
ウサギは寂しいと死ぬ? 死にません。迷信です。
死にません。迷信です。「ウサギは寂しいと死ぬ」というのは、しばしば語られる動物関連のウワサですが、迷信です。
素直に考えて「寂しいと死ぬ」という現象が本当にあり得るのか、疑問に思われる方も多いと思います。【『迷信』をマジメに解釈してみよう!】
「ウサギは寂しいと死ぬ」という言葉どおり評価すると間違った表現であり、迷信と言えますが、迷信にもしばしば教訓が隠されていることがあります。
この迷信のもとになったと推測できる、ウサギの特徴についての情報があります。
ウサギの飼い主さんには参考になるかもしれません。◉ウサギは短期間の絶食で体調を崩します◉
ウサギは食習性上、短期間でも絶食状態が続くと生命の危険につながる恐れがあります。
これがヒトやイヌ、ネコなどとの大きな違いです。
このため、一定期間ウサギが食餌を摂っていない状態に飼い主さんが気づかず、そのまま放置され続けると体調を崩して死に至る可能性があります。
つまり「寂しくて死ぬ」のではなく、飼い主さんが給餌を忘れたり、食欲低下の体調不良に気づかないなど、「ウサギに対して配慮や観察、世話が十分でなかった結果、食欲低下や絶食が原因で体調を崩し始め、最終的に死亡してしまう」恐れはあります。
給餌を忘れるなどの短期間の絶食でも、それがウサギの体調を崩すきっかけになり得ると理解できなかった飼い主さんが、ウサギの死亡原因を「世話を怠って寂しい思いをさせたために亡くなった」と思い込み、それが迷信の根拠になった可能性が考えられます。
ウサギの世話を怠ってはいけない、という意味では教訓になる話かもしれません。
ただし、「寂しいと死ぬ」という表現自体は間違いです。◉ウサギはなぜ絶食に弱いのか◉
ウサギが絶食に弱いのは、餓死しやすいからではありません。
ウサギは完全植物食(草食)動物で、食べる植物の成分の中でも最も重要なのが繊維質です。
繊維質により腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)( = 腸内細菌の集団)と消化管(胃腸)の動きを保ちます。
そして、栄養価の低い植物からエネルギーを得るために、発酵・消化するのに役立っているのが腸内細菌叢です。
腸内細菌叢がウサギの消化活動の主役であると言ってもいいかもしれません。
ウサギは、カロリー含有量が少ない植物からエネルギーや身体を構成する栄養素を得るために、腸内細菌叢の助けを借りながら消化を続け、睡眠以外の大半の時間を食餌活動に費やします。
ウサギの消化管は、ほぼ24時間働き続けるのが正常であると言えます。
極端な食餌量の低下や絶食のために、消化管内の食物、特に繊維質が不足すると、腸内細菌叢は急速に乱れ、腸管うっ滞が起こりやすくなります。
( ※ 腸管うっ滞:腸管の動きが鈍くなり、消化活動が停滞すること)
腸内細菌叢の乱れは異常な腸内ガスの発生及び発生したガスの異常貯留につながり、さらに腸管の蠕動(ぜんどう)運動が低下します。
( ※ 蠕動運動:腸管が消化活動のためにうねるような動きをする正常な運動のこと)
これらの異常が、食欲低下によって短時間で始まります。
絶食ではなおさらです。
短期間の食欲低下や絶食によって餓死するのではなく、24時間働き続けるはずのウサギの消化管は、動きが鈍くなるきっかけがあると短時間で極端な異常が起こりやすいため、生命の危険があり得るのです。
参考までに、ヒトやイヌ・ネコなどに全身麻酔をかける前には、一定時間の絶食・絶水が必要ですが、ウサギの麻酔では絶食・絶水はほとんど実施しない、または非常に短時間のみの実施にとどめます。
これは麻酔による嘔吐がウサギではほぼ起こらないだけでなく、絶食による消化管の異常発生の危険性を考慮しているためです。
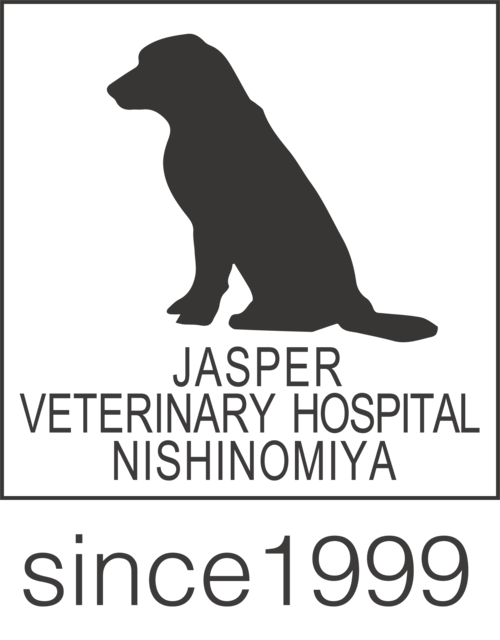
Close