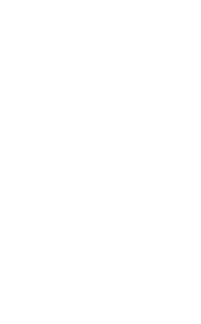- 乳児にハチミツを与えてはいけないと聞きましたが、イヌやネコにも与えてはいけませんか?
- 2025/07/15
-

-
 乳児にハチミツを与えてはいけないと聞きましたが、イヌやネコにも与えてはいけませんか?
乳児にハチミツを与えてはいけないと聞きましたが、イヌやネコにも与えてはいけませんか? 幼い動物には与えてないでください。
幼い動物には与えてないでください。ハチミツがヒトの乳児に勧められない理由は「乳児ボツリヌス症」が起こる恐れがあるからです。
このために腸内環境が未熟な1歳未満のお子さんにはハチミツもしくはハチミツを使用した食品を与えないよう、厚生労働省も指導しています。
同様の理由で、幼若な動物にもハチミツを与えるのは避けた方がいいでしょう。
そもそも、一般的な家庭動物にとってハチミツは必要性が低いので、成熟した動物にも積極的にお勧めする食品ではありません。
【乳児ボツリヌス症とは?】
ハチミツに含まれている可能性があるボツリヌス菌(Clostridium botulinum)の「芽胞(がほう)」が原因で発症します。
乳児は腸内細菌など腸内環境がまだ整っていないために、ボツリヌス菌の増殖を許してしまって発症しやすいと言われています。
症状は全身の麻痺で、「筋力低下」「声が出しにくい」「表情が消失する」などが起こります。
適切な治療で治癒するようですが、過去に死亡例もあります。
腸内環境が整った1歳以降であれば、ハチミツを食べても乳児ボツリヌス症は起こらないと言われています。
動物でも幼若期にはヒトの「乳児ボツリヌス症」と同等の問題が起こる可能性はありますので、ハチミツを与えない方がいいでしょう。
【ボツリヌス菌とは?】
ボツリヌス菌は食中毒の原因菌として知られていますが、特徴的な性質がいくつかあります。
①極めて強力な毒素を産生する危険な細菌です。ボツリヌス菌が産生する毒素は、「地下鉄サリン事件」で有名になった「サリン」、「青酸カリ」、フグ中毒の原因である「テトロドトキシン」などよりも強力で、世界最強の毒素と呼ばれています。
1グラムのボツリヌス毒素が100万人〜1,000万人以上の致死量に相当すると言われています。
現在でも、どの人工物よりも、自然毒であるボツリヌス毒素の方が強力です。
症状は全身性の麻痺で、初期は「身体の筋力低下」など、さらに「嚥下障害」や「会話の障害」が見られ、最終的に呼吸筋も麻痺するため、「呼吸不全」で死亡します。
最後まで意識は明瞭だと考えられるため、ハッキリとした意識の状態で身体が動かなくなり、呼吸ができなくなる恐怖を感じながら死亡する、かなり残酷な経過をたどることになります。
唯一の救いは、ボツリヌス毒素はタンパク質なので、加熱によってタンパク変性を起こすと失活(毒性が失われる)が可能であることです。
ただし、ボツリヌス毒素の失活のためには、80℃30分以上、もしくは100℃でも10分程度の加熱が必要です。
これはあくまで毒素対策の条件で、次項の「ボツリヌス芽胞」はこの条件では不活化できません。
一般的に大人でも発症する「ボツリヌス食中毒」はこの毒素による症状で、死亡例もあります。
ボツリヌス食中毒は、生体内にボツリヌス菌が感染するのではなく、すでにボツリヌス菌が産生した毒素を摂取することで起こります。
細菌が作り出す毒素のうち、菌体の外部に向かって生産される毒素を「菌体外毒素」と呼び、ボツリヌス毒素以外にも黄色ブドウ球菌が作り出す「エンテロトキシン」などが食中毒の原因として知られています。
動物でもボツリヌス毒素やエンテロトキシンによる食中毒は起こる恐れがあります。
②ボツリヌス菌は「芽胞」と呼ばれる「細菌のタネのようなもの」を作り、この芽胞は乾燥や熱に強いので、一般的な加熱では死滅しません。芽胞は極めて強靭で、水の沸騰温度である100℃では不活化(死滅)させることができません。
過酷な条件でも芽胞は生き残り、適した条件下で再びボツリヌス菌として増殖を始めるのです。
また、一般的な消毒剤などでも芽胞は不活化できません。
③ボツリヌス菌は「偏性嫌気性菌(へんせいけんきせいきん)」で、酸素が乏しい腸管の中などで増殖しやすくなります。「嫌気性菌(けんきせいきん)」とは、酸素が少ない方が増殖しやすい細菌のことです。
「偏性嫌気性菌」は、嫌気性菌の中でも特に酸素を嫌い、酸素がほぼ存在しない条件で増殖します。
腸管内という、酸素が乏しい環境でボツリヌス菌は活動しやすく、毒素を産生します。
参考までに、いわゆる腸内細菌も、その多くがこの偏性嫌気性菌です。
【なぜハチミツにはボツリヌス芽胞が入っている恐れがあるの?】
一般的に流通している食品の多くは、なんらかの殺菌作業など、微生物対策を施していますが、ハチミツは効果的な殺菌ができない食品だからです。
殺菌のためには加熱が最も確実ですが、ハチミツは加熱すると品質に影響があると言われており、商品価値が失われます。
特にボツリヌス菌の芽胞を不活化するには120℃4分間以上の加熱が必要で、ハチミツには適応できない条件です。
また、水のようにサラサラの液体なら「メンブランフィルター」というフィルターで細菌を除去する方法があります。
「メンブランフィルター」は、水分子などは通過できて、細菌は通過できない程度の極めて小さな穴がある膜構造で、殺菌ではありませんがこの膜を通して液体を濾過(ろか)すると、細菌を取り除くことができるのです。
残念ながら、ハチミツ原液は粘稠度が高い(水と比べてネットリしている)ために、ハチミツ自体がメンブランフィルターを通過できないので応用できません。
このため、謂わば「特例」としてハチミツは殺菌処理などが不完全な状態で流通しています。
ボツリヌス菌は、土壌中を中心に自然界に広く存在します。
野外の土壌に生えている草花から、ミツバチが自由に集めてきた蜜を利用するハチミツは、ミツバチにボツリヌス菌が付着して巣に持ち帰ることを管理・防止できないために、ボツリヌス菌や芽胞が含まれている可能性が常に否定できないのです。
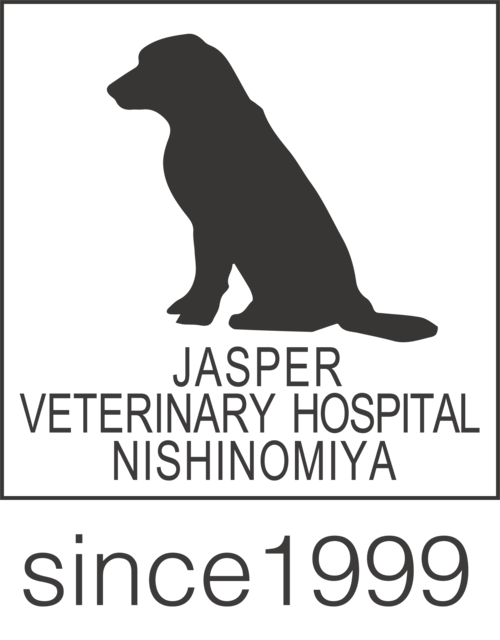
Close