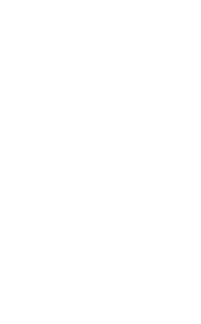- 動物病院で受診すると、たびたび体重を計測されるのはなぜですか?
- 2025/11/26
-

-
 動物病院で受診すると、たびたび体重を計測されるのはなぜですか?
動物病院で受診すると、たびたび体重を計測されるのはなぜですか? 体重の変化はその動物の健康状態・体調の目安になります。また、体重によって投与する薬剤の量が変わる場合もあるため、体重計測が必要になります。
体重の変化はその動物の健康状態・体調の目安になります。また、体重によって投与する薬剤の量が変わる場合もあるため、体重計測が必要になります。【成犬・成猫は1歳の時の体重を基準と考えましょう】
成長期が終了した後は、体重はおよそ一定であるはずです。
犬種によって差がありますが、超大型犬以外であれば生後約1年でほぼ成犬になりますから、1歳の時の体重がその後のおよその基準になると考えられます。
同様に、ほとんどの猫種でも1歳の体重がその後の基準になるでしょう。【体重は体調の指標になります】
体重の変化は体調を判断する材料のひとつになります。
体重が明確に変化していれば、その原因を検討する必要があります。
例えば食餌量が増えると体重は増加しやすく、食餌量が減ると体重は減少しやすくなります。
食餌量とは、主食だけでなく、オヤツなども全て含めた食べ物の合計量のことです。
食餌量が同じでも運動量が減ると体重は増加しやすく、運動量が増えれば体重は減りやすくなります。
食餌量や運動量が一定であるにもかかわらず、体重の大幅な変化がある場合は疾病の可能性があります。
目安として「1ヶ月間で10%の体重の増減」は健康上の問題が起きている可能性があります。
また「1週間で体重が5%増減」するのは異常が起きている可能性が高いと言えるでしょう。
5kgの動物であれば、10%は500g、5%は250gです。
500g や250gと聞けば大した変化ではないように誤解されるかもしれませんが、体重50kgのヒトで換算すると10%は5kg 、5%は2.5kgに相当します。
特別な理由が無く、比較的短期間にそのような体重変化があれば、なんらかの異常が起きている恐れがあります。【薬剤投与量は、体重を基準に決定します】
一般的な動物用薬剤は体重1kg当たりの量を算出して投与します。
具体的には「体重1kg当たり△△mg〜□□mg」のような用量です。
したがって、体重が大幅に増減すると投薬量も調整する必要が生じます。
例えば「1錠の薬剤が体重5kg以下の動物用」だった場合、4.5kgの動物は1錠の投与で効果が期待できますが、同じ動物でも体重が5.5kgに増加すると、1錠では薬剤の効果が弱く、もしくは効果が現れなくなる可能性があり、投与量を増加する必要があります。
成長期には体重が増加しますから、若齢動物のフィラリア予防薬などは成長期が終了するまで毎回体重測定しながら投与量を決めるのが原則になります。
また、標準体型でも犬種や猫種によって体重は異なります。
体重30kgを超える大型犬と3kgの小型犬では、体重が10倍違います。
人間の場合、一般平均的な成人同士であれば体重が10倍違うことはほとんど無いでしょうが、動物では充分あり得ます。
このため、人間の薬剤のように「成人は1回1錠」などの処方では、動物の体格の違いに対応できず、薬剤成分の過不足が生じてしまいます。
このような理由で動物の薬剤投与量は「体重1kg当たり△△mg〜□□mg」のように決めるのが必要かつ合理的であり、体重を確認する機会が多くなるのです。
余談になりますが、手術では麻酔薬なども動物の体重によって投与量が決まります。
大型犬の方が小型犬よりも、麻酔薬など必要な各種薬剤量が多くなりますから、手術内容が同等でも大型犬の費用の方が高額になる傾向があります。
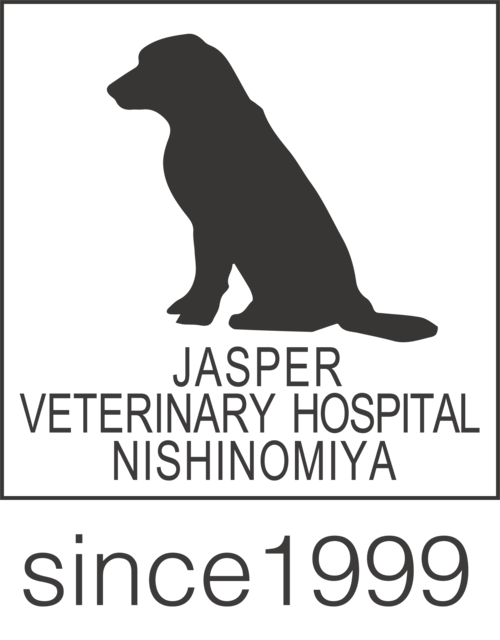
Close