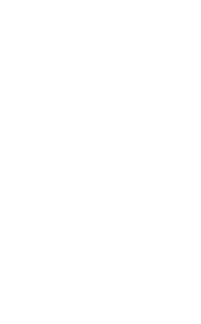- 動物は時間がわかるの?
- 2025/03/11
-

-
 動物は時間がわかるの?
動物は時間がわかるの? 体調・健康に問題が無い動物であれば、毎日の生活リズムとして、ある程度正確な時間の感覚を持っていると考えられています。
体調・健康に問題が無い動物であれば、毎日の生活リズムとして、ある程度正確な時間の感覚を持っていると考えられています。「時間がわかる」という表現が、時計を読み取れるということではなく、「生活リズムとしての時間を把握している」という意味なら、わかっている動物は多いと考えられます。
実際に、毎日同じ時間帯に同じ行動を繰り返す動物をご覧になったことがある飼い主さんもいらっしゃると思います。【時間がわかる要因】
①:体内時計(生物時計・概日リズム)
ヒトでは、脳内におよそ24時間周期のリズム信号を発振する部位があり、これによってほぼ1日の周期で体内の変化が繰り返され、地球の自転周期である24時間ごとの昼・夜の変化に同調していることがわかっています。
この現象は「体内時計」「概日リズム」などと呼ばれています。
同じ地球上で生活する動物たちも、同様の「体内時計」を持っていると考えるのが自然でしょう。
厳密にはヒトの体内時計のリズムは24時間ではなく、25時間であるとのことですし、イヌは数時間周期ではないか、という報告もあるようです。
一方、体内のコルチゾールというホルモンの分泌周期は、ヒトもイヌも午前8時〜10時頃が分泌のピークで、これを毎日繰り返していることが知られており、このことからも、体内でなんらかの24時間周期のリズムがあるのは、ほぼ確実と考えて良いでしょう。②:昼夜の周期(日照時間の周期)
野生動物であれば、日照時間が生活に大きな影響を及ぼすでしょう。
食べ物を探したり、外敵から身を守るためには、太陽光の有無が重要な条件になるはずです。
太陽光による気温・地温・水温の変化も感じ取るでしょう。
夜明けとともに活動を開始し、日没後は休む、という習性の動物であれば、日中のおよそ同じ時間帯に同じ行動を繰り返すと考えられます。
また、日差しの変化で午前〜正午〜夕方のおよその区別は可能でしょう。
みなさんが動画やテレビなどで屋外収録番組を視聴した際に、日差しの様子で収録が行われた時間帯がわかる場合があると思いますが、それと同様の感覚を動物たちも日々体験していると考えられます。
日本には四季があり夏と冬では日照時間は変化しますが、1日単位で昼の時間・夜の時間が急変するわけではありませんから、毎日の行動リズムはほぼ24時間周期が維持されるでしょう。
ただし、現代の家庭動物は電気照明という人工の光の下で生活している場合が多く、太陽光の影響、つまり「屋外が明るいか暗いか」「日照時間が長いか短いか」という意味での昼夜の影響は、野生動物より限定的かもしれません。③:習慣
飼い主さんが毎日決まった時間に食餌を与えたり、散歩に連れ出したりすると、動物はその時間を楽しみに期待して待つようになり、元々持っている体内時計のリズムが、生活 習慣により強化されることがあるでしょう。
また、動物には直接関与しない飼い主さんの行動も、毎日の習慣として繰り返されると、動物にとっても、生活リズムのポイントになり得ると思われます。
例えば、ご家族の起床時間や出勤・通学、帰宅の時間などが毎日だいたい同じであれば、それが動物にとっても生活のリズムの目安として影響することが推測できます。
動物たちは飼い主さんを観察していますから、飼い主さんの行動が動物の習慣の基準になっている場合も多いと考えられます。
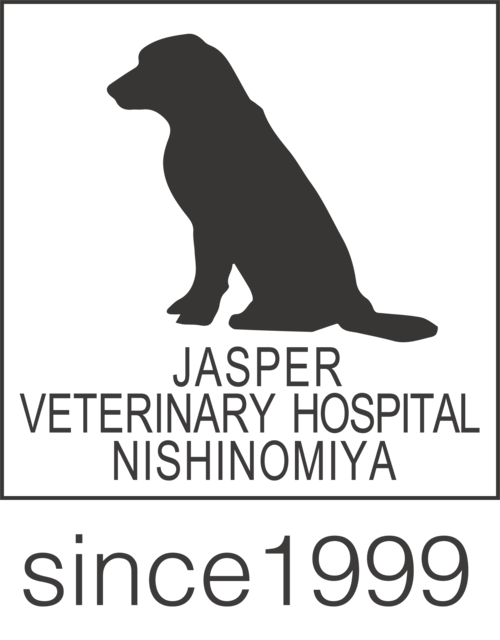
Close